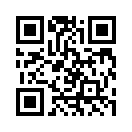2012年01月31日
お賽銭の金額
神社にお参りするときに、大抵の方はお賽銭を入れてからお参りされます。
ところで、お賽銭にはどれくらいを納めているのでしょうか。
ご縁がありますようにと5円を納める。
充分にご縁がありますようにと15円を納める。
始終ご縁がありますようにと45円を納める。
よく聞きますね。一説では とあるバス会社のガイドさんが言い始めて広がったとも。
お正月などには 福来いと2951円を納める という方もあるようです。
また、時々 「お供え」 と記して袋に入れて賽銭箱に入っていることもあります。
お賽銭とお供えは別のものでもあるのですね・・・。
このあたりのことを、いつか記事にしようと思いながら、なかなか上手く表現できずにいたのですが、今日はとても分かりよい文章を入手したので転載させてもらうことにします。

地鎮祭などで行われる、鎮物や散米の儀式も同じことです。
日々、神様にお護り頂いていることの感謝の証として供えるのが賽銭でもあるのです。 続きを読む
ところで、お賽銭にはどれくらいを納めているのでしょうか。
ご縁がありますようにと5円を納める。
充分にご縁がありますようにと15円を納める。
始終ご縁がありますようにと45円を納める。
よく聞きますね。一説では とあるバス会社のガイドさんが言い始めて広がったとも。
お正月などには 福来いと2951円を納める という方もあるようです。
また、時々 「お供え」 と記して袋に入れて賽銭箱に入っていることもあります。
お賽銭とお供えは別のものでもあるのですね・・・。
このあたりのことを、いつか記事にしようと思いながら、なかなか上手く表現できずにいたのですが、今日はとても分かりよい文章を入手したので転載させてもらうことにします。

Q お賽銭はいくら供えたらいちばん御利益がありますか?
A 金額はいくらでもかまいません。ささげる「こころ」が大切だそうです。
初詣では、神様との「ご縁」があるようにと、5円を供える人が多いのではないでしょうか。「充分ご縁があるように」と15円を、「始終ご縁があるように」と45円を供える人もいるでしょう。
本当にこれらの金額で御利益があるかというと、単なるごろ合わせで特に意味はありません。お賽銭は金額よりも神様に感謝する心が大切です。賽銭箱をよく見ると、「喜捨」と書いてあることがありますが、これは寺社などに喜んでお金をささげ、見返りを求めないという意味。願いごとがかなわなくても、神様のせいにしてはいけません。
そもそも、お賽銭にはどういう意味があるのでしょうか?お賽銭の「賽」という字は、賽の目、賽の河原と同じです。じつは、賽の字には「神仏にお礼参りをする」という意味があるのです。賽子(さいころ)も本来は占いに使う道具でした。
昔の日本人は、自然のすべてものに神様が宿ると考えていました。八百万(やおよろず)の神様をいわれるように、海には海の神、山には山の神、岩にも草木にも神様がいると信じられていたのです。私たち日本人は、それらすべてを大切にし、自然とともに生きてきました。
特に、峠や海や川などは荒ぶる神がいる危険な境界線と考えられていました。そこで、旅に出ると境界の神にささげるため、峠や海などで「手向け」の儀式が行われたのです。そのときささげたのが、絹などの布、石でできた鏡・玉・剣などの模造品。これがお賽銭の始まりです。お米をまくこともあり(散米)、今も地方の神社では賽銭箱の中にお米が入れられています。
中世以降にお金ができるとお金をまくようになり(散銭)、やがて散銭(さんせん)が賽銭(さいせん)となりました。お金が今のように賽銭箱に入れられるようになったのは、江戸時代といわれています。
ところで、お寺にも賽銭箱は置いてあります。兵庫県宝塚市にある清荒神(きよこうじん:清澄寺)では、供えられたお賽銭を持って帰ってお守りにしてもいいというユニークな風習があります。ただし、次にお参りするときは倍返しにするのがならわしだそうです。
地鎮祭などで行われる、鎮物や散米の儀式も同じことです。
日々、神様にお護り頂いていることの感謝の証として供えるのが賽銭でもあるのです。 続きを読む
2012年01月24日
厄除け祈願と初午
昨日は旧暦の年始でした。
この旧暦正月と立春までの僅かな期間が 前の年 と 新しい年 のオーバーラップする期間だと個人的には思っています。
(分かりにくい表現だと思いますが、上手に説明できない・・・)
さて、年が改まると人によっては厄年が始まります。
平成24年は、昭和46年生まれの男性、昭和55年生まれの女性が 本厄・大厄 と呼ばれる年回りです。
その前後各1年は、前厄・後厄と呼び、都合3年間は諸事に留意して過ごすのが良いと昔から伝えられています。
それ以外にも、昭和27年・昭和63年生まれの男性、昭和51年・平成6年生まれの女性は厄年と言われます。
地域によって(主に関東?)は、これらも前後1年を前厄・後厄と呼ぶようです。
また、最近では長寿社会を反映してか、女性の数え61歳も厄年(今年は昭和27年生まれ)とする地域もあるようです。
厄年には多くの方が厄除け祈願を行います。
厄除け祈願はいつ行うのが良いかということですが、年が明けると厄年が始まっているわけですから早いほうが良いですね。昔から節分までに行うのが良いとされています。
ところで、「厄除け祈願は初午に行うと聞きますが、今年の初午はいつですか?」といった主旨の問合せが毎年あります。
前述の通り、厄除け祈願は節分までに行うのが良いとされているのにこういった問合せが多いのはなぜなんでしょうか?
そもそも初午というのは お稲荷さん の縁日です。それ以前に「初午」というのはいつを指すのか説明したほうが良いかもしれませんね。
暦を見ますと、毎日それぞれに十二支があてられています。つまり 「子の日」「丑の日」・・・とあるわけです。「土用の丑」とか「酉の市」というのはそこから来ています。そして初午というのは「2月の最初の午の日」を言います。
この 初午 がお稲荷さんの縁日であるのは、和銅4年(西暦711年)の初午に、全国稲荷社の総本宮である伏見稲荷神社に神様が降り立ったと伝えられるからです。ですから全国の稲荷社では祭礼が行われます。
この初午の日というのは毎年変わりますが、大体節分のあたりになります。
どうやら、「節分までに行う厄除け祈願」 が 「厄除け祈願は節分に行う」 と変化し、更に 節分に前後する初午には稲荷社で祭礼が行われることから 「厄除け祈願は初午に行う」 と変化していったのではないかと推察します。
ですから、本来的には 初午と厄除け祈願 については、特段大きな関係はなかったと思われます。
ただ、稲荷神はお寺に祀られることも多く、厄除け祈願を行っているお寺では 「厄除けは初午に行いましょう」 ということになっていったのかもしれませんね。
伊太祁曽神社の御祭神、五十猛命は 『古事記』 の中で、災難に遭って生命を狙われた 大国主神 を救ったと記されています。
このことから、「いのち神」 という信仰が生まれ 「病難平癒」 「厄難祓い」 の祈願が多くあります。
1月15日に行われた 卯杖祭 は天下の邪気を祓う祭典のため、この日に厄除祈願をされる方も多くありますが、御祈願自体は原則的にいつでもお受けしております。
厄除け祈願を希望される方は、運気の良いお日様の高いうちにお参りください。
この旧暦正月と立春までの僅かな期間が 前の年 と 新しい年 のオーバーラップする期間だと個人的には思っています。
(分かりにくい表現だと思いますが、上手に説明できない・・・)
さて、年が改まると人によっては厄年が始まります。
平成24年は、昭和46年生まれの男性、昭和55年生まれの女性が 本厄・大厄 と呼ばれる年回りです。
その前後各1年は、前厄・後厄と呼び、都合3年間は諸事に留意して過ごすのが良いと昔から伝えられています。
それ以外にも、昭和27年・昭和63年生まれの男性、昭和51年・平成6年生まれの女性は厄年と言われます。
地域によって(主に関東?)は、これらも前後1年を前厄・後厄と呼ぶようです。
また、最近では長寿社会を反映してか、女性の数え61歳も厄年(今年は昭和27年生まれ)とする地域もあるようです。
厄年には多くの方が厄除け祈願を行います。
厄除け祈願はいつ行うのが良いかということですが、年が明けると厄年が始まっているわけですから早いほうが良いですね。昔から節分までに行うのが良いとされています。
ところで、「厄除け祈願は初午に行うと聞きますが、今年の初午はいつですか?」といった主旨の問合せが毎年あります。
前述の通り、厄除け祈願は節分までに行うのが良いとされているのにこういった問合せが多いのはなぜなんでしょうか?
そもそも初午というのは お稲荷さん の縁日です。それ以前に「初午」というのはいつを指すのか説明したほうが良いかもしれませんね。
暦を見ますと、毎日それぞれに十二支があてられています。つまり 「子の日」「丑の日」・・・とあるわけです。「土用の丑」とか「酉の市」というのはそこから来ています。そして初午というのは「2月の最初の午の日」を言います。
この 初午 がお稲荷さんの縁日であるのは、和銅4年(西暦711年)の初午に、全国稲荷社の総本宮である伏見稲荷神社に神様が降り立ったと伝えられるからです。ですから全国の稲荷社では祭礼が行われます。
この初午の日というのは毎年変わりますが、大体節分のあたりになります。
どうやら、「節分までに行う厄除け祈願」 が 「厄除け祈願は節分に行う」 と変化し、更に 節分に前後する初午には稲荷社で祭礼が行われることから 「厄除け祈願は初午に行う」 と変化していったのではないかと推察します。
ですから、本来的には 初午と厄除け祈願 については、特段大きな関係はなかったと思われます。
ただ、稲荷神はお寺に祀られることも多く、厄除け祈願を行っているお寺では 「厄除けは初午に行いましょう」 ということになっていったのかもしれませんね。
伊太祁曽神社の御祭神、五十猛命は 『古事記』 の中で、災難に遭って生命を狙われた 大国主神 を救ったと記されています。
このことから、「いのち神」 という信仰が生まれ 「病難平癒」 「厄難祓い」 の祈願が多くあります。
1月15日に行われた 卯杖祭 は天下の邪気を祓う祭典のため、この日に厄除祈願をされる方も多くありますが、御祈願自体は原則的にいつでもお受けしております。
厄除け祈願を希望される方は、運気の良いお日様の高いうちにお参りください。
2012年01月23日
旧暦正月
今日は旧暦の1月1日。つまり、明治になって太陽暦が採用されるまでは、今日が年始だったというわけです。
旧暦については「木の国神話の社 禰宜日誌」のこちらの記事を参照して下さい。
祭礼と暦1 http://itakiso.blog.shinobi.jp/Entry/247/
祭礼と暦2 http://itakiso.blog.shinobi.jp/Entry/290/
祭礼と暦3 http://itakiso.blog.shinobi.jp/Entry/291/
祭礼と暦4 http://itakiso.blog.shinobi.jp/Entry/292/
ということで、旧正月だからとお参りに来られている方がしばしば。
宮司は神社庁企画の伊勢参宮旅行の添乗で、今日は伊勢の神宮に参拝していますが、旧正月にお参りできると大変喜んでおりました。
旧暦については「木の国神話の社 禰宜日誌」のこちらの記事を参照して下さい。
祭礼と暦1 http://itakiso.blog.shinobi.jp/Entry/247/
祭礼と暦2 http://itakiso.blog.shinobi.jp/Entry/290/
祭礼と暦3 http://itakiso.blog.shinobi.jp/Entry/291/
祭礼と暦4 http://itakiso.blog.shinobi.jp/Entry/292/
ということで、旧正月だからとお参りに来られている方がしばしば。
宮司は神社庁企画の伊勢参宮旅行の添乗で、今日は伊勢の神宮に参拝していますが、旧正月にお参りできると大変喜んでおりました。
2012年01月20日
本当の絆
昨年は東日本大震災をはじめ、いろいろと災害に見舞われた年でした。和歌山県でも台風12号の影響で随分と南の方では被害が出ました。改めて、亡くなられた皆様のご冥福と、被災された皆様をお見舞い申し上げます。
さてそのような状況から、昨年は「絆」ということが再三叫ばれた年だったと思います。
地域の絆、家族の絆、とても大切なことであり、またその絆によって助けられた方も多かったと聞いています。
これを機会に、地域のつながりなどを見直す動きも活発になり、町会のイベントなどが復活したりしているとも聞きます。
こういった流れは、少し前までの人付き合いが疎かになり 「隣は何をする人ぞ」 という風潮が改まる良いことだと思うのですが、少し違うとも感じています。
地域の イベント に皆が集まって力をあわせて取り組むというのはよいのですが、所詮 イベントはどこまでいってもイベント。何らかの事情で継続に困難が見えてくると、比較的あっさりとやめてしまったりするように感じます。勿論、すべてがそうだというわけではないのですが・・・。
しかし、その地域で昔から行われていた 神社の祭礼(神事)やお寺の仏事 も、イベント同様に地域の人が集まって取り組みますが簡単に中止というわけには行きません。たとえ規模が小さくなろうとも継続しなくてはいけないものです。
そして細々とでも継続させていくことで、また賑々しく執り行える時代もやってくる、そういうものではないでしょうか?
町内会や自治会でいろいろとイベントを企画して、地域交流を深め、絆を繋ぐことに異論はありませんが、もしその地域に伝統的に行われている(もしくは、行われていた)神社やお寺の行事があればそれを再興されてはいかがでしょうか?
その方が、もっと大きな絆になると思いますし、なかなか途切れることのない強い絆になると思います。
そして、地域の絆が祭礼などの行事であるならば、家庭の絆は神棚・仏壇です。
神棚には自分達が生かされていることを神々に感謝し、仏壇には自分達へと繋がるご先祖様に感謝する。
家族揃って手を合わせることで、しっかりとした家族間の絆が深まると思います。
本当の絆とは、悠久普遍の芯を持つもの。神祭り・仏事を大切にしましょう。
さてそのような状況から、昨年は「絆」ということが再三叫ばれた年だったと思います。
地域の絆、家族の絆、とても大切なことであり、またその絆によって助けられた方も多かったと聞いています。
これを機会に、地域のつながりなどを見直す動きも活発になり、町会のイベントなどが復活したりしているとも聞きます。
こういった流れは、少し前までの人付き合いが疎かになり 「隣は何をする人ぞ」 という風潮が改まる良いことだと思うのですが、少し違うとも感じています。
地域の イベント に皆が集まって力をあわせて取り組むというのはよいのですが、所詮 イベントはどこまでいってもイベント。何らかの事情で継続に困難が見えてくると、比較的あっさりとやめてしまったりするように感じます。勿論、すべてがそうだというわけではないのですが・・・。
しかし、その地域で昔から行われていた 神社の祭礼(神事)やお寺の仏事 も、イベント同様に地域の人が集まって取り組みますが簡単に中止というわけには行きません。たとえ規模が小さくなろうとも継続しなくてはいけないものです。
そして細々とでも継続させていくことで、また賑々しく執り行える時代もやってくる、そういうものではないでしょうか?
町内会や自治会でいろいろとイベントを企画して、地域交流を深め、絆を繋ぐことに異論はありませんが、もしその地域に伝統的に行われている(もしくは、行われていた)神社やお寺の行事があればそれを再興されてはいかがでしょうか?
その方が、もっと大きな絆になると思いますし、なかなか途切れることのない強い絆になると思います。
そして、地域の絆が祭礼などの行事であるならば、家庭の絆は神棚・仏壇です。
神棚には自分達が生かされていることを神々に感謝し、仏壇には自分達へと繋がるご先祖様に感謝する。
家族揃って手を合わせることで、しっかりとした家族間の絆が深まると思います。
本当の絆とは、悠久普遍の芯を持つもの。神祭り・仏事を大切にしましょう。