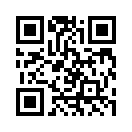2021年07月05日
七夕(たなばた) の短冊の書き方
7月7日は七夕(たなばた)です。
♫ さぁさぁの葉 さぁらさら~
♫の~き~は~に ゆ~れ~る~
と童謡で歌いますが、実際に七夕飾りを付けるのは竹。
笹なのに竹?と子供の頃は思っていましたが、要は笹竹なんですね。
といいつつ、未だによくわかっておりません・・・
さて、一般には七夕(たなばた)と呼びますが、かつての五節句では 「七夕(しちせき)の節供」 と呼んでおりました。
「桃の節供(上巳の節供)」「端午の節供」 はご存知かと思いますが、1月7日の 「人日(じんじつ)の節供」 と 9月9日の 「重陽の節供」 が五節供です。
五節句の話は横に置いて、七夕(たなばた)のお話しに戻ります。
冒頭に童謡を記したように、多くの家庭や様々な場所に笹飾りが出されます。
そして願い事を記した短冊を吊るすのですが、これっていつまでに吊ったら良いでしょうか?
七夕は7月7日の行事ですが、7月7日(から8日にかけて)の夜ではないんですね。
多くの場所では7月7日未明に神事が行われるようです。(当社では七夕の行事がないので)
また、七夕で願い事を行うようになったルーツとも言える 「乞巧奠(きっこうてん)」 という行事は、織姫に対して手芸の上達を願う祭りとされているため、七夕で短冊に書く願い事は 「芸事に限る」 とする地域もあるようです。
いずれにせよ、様々な要素が複雑に入り混じって現代の 七夕(たなばた)行事 があるので、「どうしなくてはならない」 ということはありませんが、もし短冊に願い事を書かれるのであれば、6日の夜までに書かれて吊っている方が良いと思います。
♫ さぁさぁの葉 さぁらさら~
♫の~き~は~に ゆ~れ~る~
と童謡で歌いますが、実際に七夕飾りを付けるのは竹。
笹なのに竹?と子供の頃は思っていましたが、要は笹竹なんですね。
といいつつ、未だによくわかっておりません・・・
さて、一般には七夕(たなばた)と呼びますが、かつての五節句では 「七夕(しちせき)の節供」 と呼んでおりました。
「桃の節供(上巳の節供)」「端午の節供」 はご存知かと思いますが、1月7日の 「人日(じんじつ)の節供」 と 9月9日の 「重陽の節供」 が五節供です。
五節句の話は横に置いて、七夕(たなばた)のお話しに戻ります。
冒頭に童謡を記したように、多くの家庭や様々な場所に笹飾りが出されます。
そして願い事を記した短冊を吊るすのですが、これっていつまでに吊ったら良いでしょうか?
七夕は7月7日の行事ですが、7月7日(から8日にかけて)の夜ではないんですね。
多くの場所では7月7日未明に神事が行われるようです。(当社では七夕の行事がないので)
また、七夕で願い事を行うようになったルーツとも言える 「乞巧奠(きっこうてん)」 という行事は、織姫に対して手芸の上達を願う祭りとされているため、七夕で短冊に書く願い事は 「芸事に限る」 とする地域もあるようです。
いずれにせよ、様々な要素が複雑に入り混じって現代の 七夕(たなばた)行事 があるので、「どうしなくてはならない」 ということはありませんが、もし短冊に願い事を書かれるのであれば、6日の夜までに書かれて吊っている方が良いと思います。
Posted by 木霊 at 14:48│Comments(0)
│祭礼・行事
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。