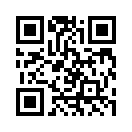2020年03月26日
2020年03月10日
御朱印帳の取り扱い
平成から令和に御代替わりの時、多くの神社では御朱印を求める参拝者で溢れかえっていました。
わずか1年足らず前の出来事です。
その少し前から御朱印ブームというのは始めっていたが、御代替わりを境に尚一層著しくなった気がします。
御朱印を神社仏閣から頂いてきてインターネットオークションなどで転売する輩が顕著になったのもこの頃でしょうか。
御朱印の受け方や御朱印帳の扱い方等については、様々なところでいろいろと記されているのでそちらに譲るとして、今回話題にしたいのは持ち主がいなくなった御朱印帳の扱いについてです。
まずは 『神社新報』 の以下の記事をご覧ください。
(画像の下に一部抜粋してテキスト化しています)

《 抜 粋 》
(前略)
御朱印は本来納経といって、社寺参拝の折に般若心経一巻を書写奉納した証のものであったのだから、せめて大祓詞一巻の書写奉納を義務付けるほどの信仰心が必要なのだらうが、その声は聞こえてこない。
だが流行はいつか廃れるし、熱心に社寺を巡拝して御朱印を集めた人も年をとる。さう考へるとこの流行が醒めた、今後ある時に大量に御朱印帳が処分される時期が来るといふことである。故人の意を汲んで社寺に納めてお焚上げにするならいいが、これが古紙として回収されることはいかがであらうか。御朱印は神札と同様のものとの考へもある。
流行が去り、所有者が亡くなったら、それは過去の旅の記憶に過ぎず、本人以外には無用のものとならう。そしていつか平成から令和に及ぶこの時期の御朱印が大量に古道具屋に出廻ったり、廃棄される時が来るのである。
(中略)御朱印帳は神仏の参拝の証であり、単なる名所巡りのスタンプ帳とは違って、粗末に扱ふものではないといふこと。また所有者の歿後も、その神聖性を保持し、処分にあたってはせめてお焚上げをするべきであるとの二点をぜひとも啓発せねばならない時期になってはゐまいかと思ふのである。
御朱印を集めて回る人たちの中には、一部不心得者がおり、その少数派の方々の行動が原因となって一部の神社では朱印を書くことを取りやめたり、朱印帳の扱いについて独自の規則を設けているところがあります。(中には神社の独自規則が行き過ぎているように見受けられる場合もあるが・・・)
そういった不逞の輩については今回は触れず、大多数のちゃんと神社仏閣を参拝して御朱印を集めて回っている方々の朱印帳についてのお話です。
御本人は信仰心を持ち、敬虔なものとして御朱印帳を扱っていたとしても、御本人が亡くなった後、果たしてその御朱印帳はどの様な扱いをされるのだろうかというのが、この投稿に記されたところです。
これまで、御神札やお守りについては、故人が祀っていた、所有していたものについて、その扱いが記されているものもありました。
改めて記すならば、
授かった神社や仏閣に出向いてこれまで護っていただいた御礼の参拝をして、その神社仏閣に御神札やお守りを返却する。
遠方などで上記が行えない場合は、やむを得ず近くの神社仏閣に持参してお焚上げを依頼する。(神社のものは神社へ、お寺のものはお寺へ)
また、故人が病に臥せっていた場合で、家族親族や友人が病気平癒の祈願などを行っていた場合は、当該神社仏閣に詣でて帰幽(亡くなったこと)奉告を行うこと。
ということです。
近年までこれほどまでの御朱印ブームはありませんでしたから、御朱印帳についてこの様な記述はなかったのだと思います。
また、仮にそこまで書かれていなくても、故人の思いを汲み取って、ご遺族は然るべき処置をするだろうという憶測もあったと思います。
もし、身の回りで御朱印帳の遺品が出てくることがありましたら、然るべくよろしくお願いいたします。
勿論、神社仏閣に持参してお焚上げをするだけが方法ではありません。
その朱印帳を引き継いて、各地の神社仏閣の御朱印を集める(特に全国一の宮朱印帳などの類)のも1つの方法ですし、故人の思いが詰まったものとして末永く保管しておくのも1つの方法です。
1つだけ願うとすれば、ゴミとして処分することだけは夢々なさりませんように・・・。
2020年03月03日
567でコロナ
夕刊フジ WEB版 の記事を転載します。
韓国・文政権が日本にすり寄り「共に危機を克服しよう」 新型肺炎の“特効薬”アビガン目当て? 苦境脱出へ輸入模索
https://www.zakzak.co.jp/soc/news/200302/for2003020004-n1.html
2020.3.2
新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、韓国の文在寅(ムン・ジェイン)大統領が日本にすり寄ってきた。日本の朝鮮半島統治に抵抗して1919年に起きた対日独立運動「三・一独立運動」の式典で、いつもの「反日」発言を控えたのだ。一体、狙いは何か。
「日本は常に最も近い隣国だ。共に新型コロナウイルスの危機を克服し、未来志向の協力関係に向けて努力しよう」
文氏は1日、ソウルでの式典でこう演説した。新型肺炎(COVID19)対策に多くの時間を割き、「われわれは必ずコロナウイルスに勝ち、経済をよみがえらせる」と決意を語った。
一方、対日関係については、「過去を直視してこそ傷を克服し、未来に進める。過去は忘れられないが、われわれは過去にとどまることもない」と述べるにとどめた。
過去の演説で、いわゆる徴用工や慰安婦などの問題を取り上げて、日本を徹底的に批判してきたのとは大違いだ。
韓国では、新型コロナウイルスの感染拡大が止まらない。1日だけで感染者は586人増え、感染者計3776人、死者18人に達した。ここで歯止めをかけなければ、4月の国会議員選挙での与党への大逆風は確実だ。
この苦境を脱するため、文政権は、日本が新型インフルエンザ薬として200万人分を備蓄し、新型コロナウイルスへの有効性も期待されている治療薬「アビガン」に注目しており、輸入を模索している。
だが、「アビガン」は日本人の命を守る薬だ。東京五輪を「放射能五輪」と揶揄(やゆ)する国に回す余裕はない。
朝鮮近現代史研究所所長の松木國俊氏は「文政権は『アビガン』をノドから手が出るほど欲しがっている。だが、韓国は、日本が戦後復興などで多額の援助をしても一切感謝しなかった。現状が落ち着けば、また『反日』に転じるのは明らかだ。日本人優先を維持すべきだ」と語っている。
2020年03月03日
新型コロナウィルスの蔓延と神社の祭礼

今、巷では新型コロナウィルスの対策と感染状況が大きな関心事になっています。
当初 「新型ウィルス」 で良いのではないか、と思っていましたが、少し前に猛威を奮ったSARS(サーズ:重症急性呼吸器症候群)とかMARS(マーズ:中東呼吸器症候群)も 「コロナウィルス」 によるものなので、今回のものが 「新型コロナウィルス」 と呼ばれるのだそうです。
さて、この新型コロナウィルスについてはまだまだ未解明なことが多いためその感染が広がっていますが、最近の情報では空気感染力は極めて弱く、飛沫感染や接触感染で広まっていると云われています。
また感染していても発症していない、いわゆる潜伏期間であっても感染力があり、咳やクシャミなどで拡散したり、その際の粘液がモノを媒介して感染するようです。
そのため、うがい・手洗いといった方策が有効だと云われています。
モノを媒介してウィルス感染する危険性があるということで、公共交通機関の手すりやつり革、スポーツジムの機器や、バイキング形式のレストランでのトングなどに気をつけたほうが良いという情報も流れています。
神社でも不特定多数の参拝者が使用する手水やその柄杓、また拝殿前の鈴を撤去するところもあるようです。
伊太祁曽神社には拝殿に鈴は掛かっておりませんので、特にその面における心配はありません。
また手水に関しては今の所、柄杓の撤去や水を止めるということも行っておりません。
手水に使用する水は常に手水鉢から溢れるように流しており、また多くの方が使用する柄杓につきましても、正しい作法でお使いいただけば問題ないと考えております。
確かに様々な危険性を考慮して柄杓を撤するという方法もあるとは思いますが、ここは正しい作法を再確認することで 柄杓経路による感染防止 としたいと思っております。
改めて手水の際の柄杓の使い方について要点を記しておくならば
・柄杓に直接口をつけて口を清めない
・使用したあとは持ち手を水で流して清める
この2点です。つまり接触感染が原因ではありますが、不必要に柄杓に触れないのが作法であり、また接触した部分については最後に使用者が清めるのが作法なのです。
アルコール除菌に比べれば、流水で清めることには不足があるかもしれませんが、そこを細かく言うならばおよそ一切の外出を禁止するのに等しいことだと思います。
さて、話が横道にそれましたが、3月に入り神社では 春祭り が行われるところも多くあります。
全ての春祭りがそうであるとは言いませんが、いつくかの神社で行われる春祭りは 「鎮花祭(ちんかさい:はなしずめのまつり)」 に由来するところもあると思います。
鎮花祭については平安時代の法令集である 「大宝令」 にも記されており、春の花びらが散るときに疫神が流行病を引き起こすために、それを鎮める祭りとされています。
「まつり」 というと多くの人が集まりますので、昨今の状況を鑑みると 「今年の祭礼は中止」 とするところもあるかもしれませんし、また 「例年通り斎行」 となれば 「なぜ行うのだ」 と批判的な意見も出てくるかもしれません。
確かに新型コロナウィルスの感染状況を考えると多くの人が集まる行事は避けるべしなのかもしれませんが、祭祀の本質に 「疫病退散」 がある場合にはむしろ積極的に祭礼を行うべしと思います。
勿論、感染拡大を防ぐために十分な注意が必要であり、場合によっては人の集まる所謂 「神賑行事」 は中止するべしとは思いますが、祭祀自体を中止することはその主旨に反すると考えます。
また春祭りではありませんが、有名な京都の八坂神社の祇園祭は、まさに疫病退散を目的として始まったお祭りです。
神社の祭礼は単なるイベントではありません。祈りの場として、感謝の場として行われるものです。
その神社の祭礼がどの様な由来があるのか、この機会に見直してみてはいかがでしょうか?