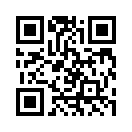2014年08月15日
欲しがりません・・・勝つまでは・・・
終戦記念日という人もいますが、この表現は適切ではないと思ってます。
ちなみに、本当の意味で(国際認識として)日本が終戦を迎えるのはもう少し後なのですが、まぁそれはそれとして・・・。
「欲しがりません勝つまでは」
「贅沢は敵だ」
などというのは戦時中の標語として有名ですね。
「贅沢は素敵だ」なんて変形があったとか、なかったとか・・・。
さて、先日朝日新聞社はこれまで報道してきた日本軍による従軍慰安婦の強制連行について誤報であったと発表しました。
誤報でなく捏造であって、その捏造の為に我が国はいったいどれほどの不利益を被ったのか真摯に考えてほしいと思うところではありますが、この新聞社はどこ吹く風な様子です。この件についても書きたいことは沢山ありますが今日は触れません。
いずれにしても、この従軍慰安婦の強制連行のような事実確認が取れないことも沢山吹き込まれて自虐史観の下で教育を受けてきた我々戦後世代には、自国に自信を持てない人が沢山います。しかし、最近は本当の日本を知ろうという人たちが随分と増えてきていると感じます。
先日、とある友人がSNSに 「この誤った歴史認識は敗戦によってもたらされた勝者目線の歴史であるから、改めるにはもう一度戦争をして勝つしかないのかもしれない」 と書いていました。
しかし彼は同時に、「原子爆弾が投下されて街が壊滅的に破壊された中で、彼の土地の人たちは新型爆弾を落とした連合軍を憎むのではなく、街を復興させなくてはならないと決意した」 とも書いていました。ここにある意味日本民族の素晴らしさがあるとも。
世界の常識からすると 「再び戦火を交えて勝利しない限り、敗者は勝者の意の下に動かされてしまう」 のかもしれません。
我々日本人も例に漏れず占領軍が残していった歴史観、教育方針、憲法などの諸制度等々に縛られてきました。
しかし停戦から70年近くを経た近年、ようやくこれらの呪縛から抜け出そうともがきだし、否、もがけるようになってきました。
私は捻じ曲げられた歴史観などを元に戻すには、倍の時間がかかるだろうと思っています。
つまり、今大きく舵を切れても、元に戻せるのは150年先ということです。当然、今生きている人たちは誰一人としてその成果を目にすることはできません。
それでも、やらなくてはいけないことです。日本という国が、日本という形で未来も存続するために。日本人が、日本人として生活するために。
本当の日本を取り戻すことは 「欲しがりません、勝つまでは」 ではなく、実行したいものです。
2014年08月09日
神宮大麻

お伊勢さんのお札を 神宮大麻 といいます。「お伊勢さん」とか「お祓い大麻」などとも呼ばれます。
神棚には神宮大麻と氏神様のお札をお祀りします。他に崇敬する神社があればそちらのお札もあわせてお祀りしますが、少なくとも神棚には2枚のお札が納められているのが普通の状態です。
神宮大麻は、原則として全国どこの神社でも受けることができます。
ところで、神宮大麻には実は3種類あるのを御存知ですか?
一般に広く知られる 神宮大麻 とは別に 中大麻(ちゅうたいま)、大大麻(だいたいま) と呼ばれるお札があります。
(写真の左から神宮大麻、中大麻、大大麻)
中大麻や大大麻を置いている神社は少ないかもしれません。
少なくとも和歌山県内では伊太祁曽神社だけの様です。
先日お参りに来た方が、この大きさのお伊勢さんのお札が欲しいと云われました。中大麻です。
たまたま今年の分がまだあったのでお頒ちすることができました。
2014年08月02日
道徳教育

文部科学省では、今年度から義務教育課程における道徳教育について、新たに冊子を作成し全国の小中学校に配布することにしたそうです。
そしてこの冊子を用いて道徳の授業を行うとともに、冊子は児童・生徒がそれぞれ自宅に持ち帰り、自分の家族や地域の人達とも一緒に学習するように通達しているそうです。
文科省が作成したこの冊子については、文科省のサイトで全ページを見ることができます。
文部科学省>教育>小学校、中学校、高等学校>道徳教育
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/doutoku/index.htm
どの冊子にも冒頭に 「この本の使い方」 として、学校の道徳の時間だけでなく、休み時間や放課後に活用したり、家の人や地域の人達と一緒に考えたりするようにも記されています。
しかし、現実には道徳の授業の初めに冊子を配布し授業が終わったらその都度回収する学級や、酷いところになると道徳の授業そのものを行っていない学級もあることが分かってきました。
そこで、私共若手神職の全国組織である神道青年全国協議会が実態調査を行うべく、全国の会員にそれぞれの子供などが通う小中学校における道徳教育の実態について報告を求めることとなりました。
私も、知人などにそれぞれのお子さんがどのように道徳の授業が行われているのか聞いてみました。
14学級の情報が集まりましたが、なんと文科省の通達通り児童・生徒に道徳の冊子を配布しているのはわずかに1学級でした。
それ以外の多くの学級では、道徳の時間に配布して授業が終わると回収して保管するという形態をとっているようです。
そして、多くの学級では道徳の時間は週に1回程度行われているようですが、中には教科書の使用は月に1回程度で残りの時間は図書室で子供がそれぞれ好きな本を読む「読書の時間」に当てている学級や、さらには道徳の時間をとっていない学級もありました。
何故、これほどまで多くの学級が文科省の通達を違えた授業を行うのか、その理由は分かりません。
もしかしたら文科省が作成した「わたしたちの道徳」という冊子の内容が不適切なのかもしれませんね。
この冊子の内容が適切なのかそうではないのかは、このページをご覧になった皆さん自身が確かめて判断していただきたいと思います。
「わたしたちの道徳」は以下のリンクより、小中学校各学年の冊子それぞれを全ページ閲覧できます。
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/doutoku/index.htm