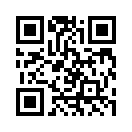2018年05月14日
京都大学の立て看板
京都大学のキャンパスから外に向けて掲げられた立て看板が話題になっています。
平成30年5月13日付読売新聞朝刊の「編集手帳」にはこんな風に記載がありました。

なんとなくもっともらしい事が書かれている気がして 「なるほど」 と思ってしまう人もいるかも知れませんが、この文章はちょっとおかしいと思いませんか?
以前であればそのままブログを続けて書いていましたが、少し改行を多く取るので、もう一度読み返して考えてみて下さい。
続きを読む
平成30年5月13日付読売新聞朝刊の「編集手帳」にはこんな風に記載がありました。

戦前の、ある旧制中学の話だ。紳士たれ、と語る校長はライバル校にイートンやハローなど英国のエリート養成校の名を挙げた。ゲートル着用を命じる将校には「我が校は自由を尊重する」とやり返した
教師はシェークスピアやノバーリスを教えた。スボンの折り目だけはきちんとつけるように。学校からの指示に、生徒は毎晩、霧吹き、寝押しを欠かさなかったという
抵抗や反抗することではない。自分はこう生きるのだと、強い意志を示すことが自由だと教わった―。この中学に通い、後に京都大の学長を務めた西島安則さんの弁である
これも自由を巡る論争か。京大のキャンパスの外周、学生らが公道に立てかけた数々の看板は条例違反だと、大学が撤去に乗り出した。「立て看板は京大の文化。自由な学風はどうなる」。学生が反発し、騒動になっている。
双方、たかがタテカン、されどタテカンなのだろう。「結晶は完璧になると成長しない。整いすぎる時には異質なものが必要だ」。西島さんはこんな言葉も遺した。正論、大人の常識にどう抗うか。自由を持ち出す学生には覚悟と独創性がいる。
平成30年5月13日 読売新聞 編集手帳
なんとなくもっともらしい事が書かれている気がして 「なるほど」 と思ってしまう人もいるかも知れませんが、この文章はちょっとおかしいと思いませんか?
以前であればそのままブログを続けて書いていましたが、少し改行を多く取るので、もう一度読み返して考えてみて下さい。
続きを読む
2018年05月14日
奉納演奏
奉納演奏 という言葉を聞いたことがあると思います。
神社やお寺の境内で音楽などを奏でる行事が行われると、大抵「奉納演奏」と書かれていたりします。
でも、神社仏閣の境内で演奏することが「奉納演奏」ではありません。
つい先日、そんな話を ”神職ではない方” としておりましたので、ちょっと記しておきたいと思います。
お話したお相手は、とある会社の代表者。
神社が大好きでいろんな神社にお参りに行かれたりするそうですが、時々奉納演奏ではない奉納演奏を目にすると言います。
この時点で何を仰っしゃりたいのか概ね想像はつきましたが、続けてお話を伺うと、私と全く同じ考え方でした。
奉納演奏というのは、文字通り演奏を奉納することです。
「奉納」ですから、その対象は神社であれば神様、お寺であれば仏様な訳です。
ところが「奉納演奏」と称しながら、神社の本殿や、お寺の本堂を背にして、集まった人たちに対して演奏している写真をしばしば目にします。
これは 「奉納演奏」 ではありません。
ちょっと想像してみて下さい。
あなたがコンサートやライブに行くとします。会場につくと、あなたの席は演奏者の後ろでした。
つまり演奏者の背中は見えるけど、顔は見えない場所があなたのお席です。
普通そういう席はないと思いますが、極稀に会場の都合でそういうお席が提供される場合もありますね。
でも、それがVIP席だったらどうでしょうか?
すくなくともVIP席を準備しましたと言われて、そのアーティストの顔も見ることが出来ない、舞台の後方の席です。
勿論、舞台正面には席があります。
本殿や本堂を背にした舞台での演奏は、つまりは神様や仏様は今記した、舞台背面の席で聞くことになるわけです。
しかし「奉納演奏」ですから神様仏様がVIP・・・。
これは、演奏する側も気づかなくてはならないのですが、やはりそれ以上にその神社の神職や、そのお寺の僧侶がもっと気づかなくてはなりませんし、注意しなくてはならないと思います。
伊太祁曽神社の場合、奉納演奏をしたいとお申し出がありましたら、その旨をちゃんと理解してもらいます。
つまり 「神様に対して演奏したいのか、それともこの場所で多くの人たちに聞いてもらいたいのか」 ここを明確にしてもらいます。
神様に聞いていただきたいという趣旨でしたら、当日はまず正式参拝をしていただき、引き続いて神前にて神様に相対して演奏して頂きます。
折角の機会ですので、演奏を聞きたいという方もいると思いますので、その方々には奏者の左右にお席を設ける場合はあります。
また、それなりに大規模で取り組む場合には奉納舞台での演奏をお願いしています。
勿論奉納舞台ですから、舞台正面は本殿を向いています。
但し、それなり本殿まで距離がありますから、舞台の前に人間の観客席を設けることは可能です。
神様の方を向きながら、多くの方にも聞いていただくことができる設営の 「奉納演奏」 も可能です。
そして、単に神社という空間を使って演奏を行いたいという趣旨の場合、その目的や内容によっては許可する場合があります。
但し、演奏場所として拝殿前はお断りをしています。いわゆる外苑部分などでの取り組みをお願いしています。
神社やお寺の境内で音楽などを奏でる行事が行われると、大抵「奉納演奏」と書かれていたりします。
でも、神社仏閣の境内で演奏することが「奉納演奏」ではありません。
つい先日、そんな話を ”神職ではない方” としておりましたので、ちょっと記しておきたいと思います。
お話したお相手は、とある会社の代表者。
神社が大好きでいろんな神社にお参りに行かれたりするそうですが、時々奉納演奏ではない奉納演奏を目にすると言います。
この時点で何を仰っしゃりたいのか概ね想像はつきましたが、続けてお話を伺うと、私と全く同じ考え方でした。
奉納演奏というのは、文字通り演奏を奉納することです。
「奉納」ですから、その対象は神社であれば神様、お寺であれば仏様な訳です。
ところが「奉納演奏」と称しながら、神社の本殿や、お寺の本堂を背にして、集まった人たちに対して演奏している写真をしばしば目にします。
これは 「奉納演奏」 ではありません。
ちょっと想像してみて下さい。
あなたがコンサートやライブに行くとします。会場につくと、あなたの席は演奏者の後ろでした。
つまり演奏者の背中は見えるけど、顔は見えない場所があなたのお席です。
普通そういう席はないと思いますが、極稀に会場の都合でそういうお席が提供される場合もありますね。
でも、それがVIP席だったらどうでしょうか?
すくなくともVIP席を準備しましたと言われて、そのアーティストの顔も見ることが出来ない、舞台の後方の席です。
勿論、舞台正面には席があります。
本殿や本堂を背にした舞台での演奏は、つまりは神様や仏様は今記した、舞台背面の席で聞くことになるわけです。
しかし「奉納演奏」ですから神様仏様がVIP・・・。
これは、演奏する側も気づかなくてはならないのですが、やはりそれ以上にその神社の神職や、そのお寺の僧侶がもっと気づかなくてはなりませんし、注意しなくてはならないと思います。
伊太祁曽神社の場合、奉納演奏をしたいとお申し出がありましたら、その旨をちゃんと理解してもらいます。
つまり 「神様に対して演奏したいのか、それともこの場所で多くの人たちに聞いてもらいたいのか」 ここを明確にしてもらいます。
神様に聞いていただきたいという趣旨でしたら、当日はまず正式参拝をしていただき、引き続いて神前にて神様に相対して演奏して頂きます。
折角の機会ですので、演奏を聞きたいという方もいると思いますので、その方々には奏者の左右にお席を設ける場合はあります。
また、それなりに大規模で取り組む場合には奉納舞台での演奏をお願いしています。
勿論奉納舞台ですから、舞台正面は本殿を向いています。
但し、それなり本殿まで距離がありますから、舞台の前に人間の観客席を設けることは可能です。
神様の方を向きながら、多くの方にも聞いていただくことができる設営の 「奉納演奏」 も可能です。
そして、単に神社という空間を使って演奏を行いたいという趣旨の場合、その目的や内容によっては許可する場合があります。
但し、演奏場所として拝殿前はお断りをしています。いわゆる外苑部分などでの取り組みをお願いしています。
2018年05月02日
神社の参道の中央を歩いてはいけないのか?
ここ数年、神社での参拝作法などをテレビや雑誌などで取り上げてくれています。
一時期に比べると、手水をきちっと取ってから参拝する人が増えたようにも思います。
ところで、神社での参拝作法を説明する一連の流れの中で、「参道の中心は神様の通り道だから通ってはならない」というのがあります。
確かにもっともらしく聞こえるので実践している参拝者も多くいらっしゃいますし、同行者が参道の中心を歩いていると注意している人もしばしば目にします。
一方で、我々神職は祭典での参進などでは参道の中心(正確には少しだけ中心を外すのですが)を歩きます。
参道の中心を歩くことについては興味深い資料があります。
江戸時代前期に編集されたとされる 『神拝式類集』 という書物に次にような文章があるそうです。
およそ参道の中央を歩行するのこと、思慮あるべし とでも読むのでしょうか。
「参道の中央を歩くときは慎みの心を持ちなさい」という意味であろうと解釈されています。
この書は参宮の次第について纏めたものとのことで、つまりは神職ではなく一般に向けたものということになります。
したがって、江戸時代前期頃においては 「参道の中央を歩くべきではない」 ということにはなっていないのですね。
これは非常に興味深いことです。
一時期に比べると、手水をきちっと取ってから参拝する人が増えたようにも思います。
ところで、神社での参拝作法を説明する一連の流れの中で、「参道の中心は神様の通り道だから通ってはならない」というのがあります。
確かにもっともらしく聞こえるので実践している参拝者も多くいらっしゃいますし、同行者が参道の中心を歩いていると注意している人もしばしば目にします。
一方で、我々神職は祭典での参進などでは参道の中心(正確には少しだけ中心を外すのですが)を歩きます。
参道の中心を歩くことについては興味深い資料があります。
江戸時代前期に編集されたとされる 『神拝式類集』 という書物に次にような文章があるそうです。
凡参道歩行於中央事、可有思慮
およそ参道の中央を歩行するのこと、思慮あるべし とでも読むのでしょうか。
「参道の中央を歩くときは慎みの心を持ちなさい」という意味であろうと解釈されています。
この書は参宮の次第について纏めたものとのことで、つまりは神職ではなく一般に向けたものということになります。
したがって、江戸時代前期頃においては 「参道の中央を歩くべきではない」 ということにはなっていないのですね。
これは非常に興味深いことです。