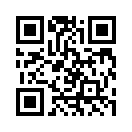2011年06月30日
お礼参り
今日は 「病気平癒のお礼参り」 の参拝奉仕をしました。
先日も同様に 「病気が治ったのでお礼参拝を」 という方が来られ、御垣内参拝を。
多くの方が神社で祈願をされますが、あまり御礼参拝ってないんですね。
人間に対してでも、頼みごとをしたらお礼をしますが、神様に対しても同じ。
ご祈祷と同じように中に入ってまでされなくても結構ですが、やはりちゃんと奉告の参拝はしましょうね。
先日も同様に 「病気が治ったのでお礼参拝を」 という方が来られ、御垣内参拝を。
多くの方が神社で祈願をされますが、あまり御礼参拝ってないんですね。
人間に対してでも、頼みごとをしたらお礼をしますが、神様に対しても同じ。
ご祈祷と同じように中に入ってまでされなくても結構ですが、やはりちゃんと奉告の参拝はしましょうね。
2011年06月29日
やすべえ
今日はお休みだったので、お昼を外食にしました。
神社周辺にはあまり飲食店がないので外食するとなると車で少し移動しなくてはならないんですね。
来客で一緒にお昼を、となると結構困ったりします。
時々食べに行く焼肉屋さんがランチもやっているということだったので行ってきました。
ちょっと前に来客があった時にここへ連れて行ったのですが、なかなか良かったので。
前回は タンシチュー定食 を食べました(なかなかおいしかったですよ)が、同じではつまらないので今日はカレーに。
このカレーもなかなかインパクト大でした。

写真のカレー中央にあるのは牛肉。こんな大きな塊が3つも!
ルーの味も香りが高くなかなかgoodでした。
続きを読む
神社周辺にはあまり飲食店がないので外食するとなると車で少し移動しなくてはならないんですね。
来客で一緒にお昼を、となると結構困ったりします。
時々食べに行く焼肉屋さんがランチもやっているということだったので行ってきました。
ちょっと前に来客があった時にここへ連れて行ったのですが、なかなか良かったので。
前回は タンシチュー定食 を食べました(なかなかおいしかったですよ)が、同じではつまらないので今日はカレーに。
このカレーもなかなかインパクト大でした。

写真のカレー中央にあるのは牛肉。こんな大きな塊が3つも!
ルーの味も香りが高くなかなかgoodでした。
続きを読む
2011年06月25日
花火で復興支援
東日本大震災の犠牲者追悼と、被災地復興支援のため、8月11日に大きく被災した東北3県の太平洋沿岸で一斉に花火を打ち上げるイベント企画があります。
太平洋沿岸10数カ所で、8月11日(木)に花火を一斉に打ち上げる復興支援プロジェクト
http://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000003380.html
FaceBookをしている仲間が紹介していました。
1人1口1,000円から協賛できるそうです。
太平洋沿岸10数カ所で、8月11日(木)に花火を一斉に打ち上げる復興支援プロジェクト
http://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000003380.html
FaceBookをしている仲間が紹介していました。
1人1口1,000円から協賛できるそうです。
2011年06月20日
2011年06月19日
毛付け講
「毛付け講(けつけこう)」って知っていますか?
育毛・増毛祈願の集まりではないですよ。
実は、お米の豊作祈願なんですね。
水田に稲を植えた様子が ”毛が生えてきた様子” に似ているということで、田植えを ”毛付け” と呼ぶことがあります。
田植えが終わったこの時期に、今年の稲も丈夫に育って、沢山お米が取れるようにと祈願する集まりを 「毛付け講」 と呼ぶのです。
今日は、毎年恒例で来られる 「毛付け講」 のお参りがありました。
こういう習慣も、だんだんと廃れていってしまっている、日本の美しい伝統だと思いませんか?
育毛・増毛祈願の集まりではないですよ。
実は、お米の豊作祈願なんですね。
水田に稲を植えた様子が ”毛が生えてきた様子” に似ているということで、田植えを ”毛付け” と呼ぶことがあります。
田植えが終わったこの時期に、今年の稲も丈夫に育って、沢山お米が取れるようにと祈願する集まりを 「毛付け講」 と呼ぶのです。
今日は、毎年恒例で来られる 「毛付け講」 のお参りがありました。
こういう習慣も、だんだんと廃れていってしまっている、日本の美しい伝統だと思いませんか?
2011年06月18日
酔鯨
土佐のお酒で 「酔鯨(すいげい)」 というのがあります。
鯨が酔うのですからすごいですね。さすが 土佐! って感じです。

実は、この酔鯨というお酒、すごく好きなんですね。
ただ、なかなか見かけることがない。
先日和歌山のある酒屋さんで見かけましたので迷わず購入。
で、完飲です。(ん?完食にたいして完飲。勿論造語です。)
鯨が酔うのですからすごいですね。さすが 土佐! って感じです。

実は、この酔鯨というお酒、すごく好きなんですね。
ただ、なかなか見かけることがない。
先日和歌山のある酒屋さんで見かけましたので迷わず購入。
で、完飲です。(ん?完食にたいして完飲。勿論造語です。)
2011年06月17日
住吉大社(大阪府)のお田植え神事
日本の三大御田植祭とされているのは、
・神宮(伊勢の神宮、別宮である伊雑宮で行われる)
・香取神宮(千葉県)
・住吉大社(大阪府)
の3つ。学生のときに神宮のお田植祭は何度か拝見させてもらいました。今回は住吉大社の御田植神事に参列させていただきました。
まずは、第一本殿で祭典が執り行われます。また祭典に先立って奉仕する植女などに関する儀式もありますが秘事でもありここでは割愛。宮司の祝詞奏上が終わって、早苗が渡されるところから写真を交えて簡単に紹介します。















午後1時に第一本殿で祭典が執り行われ、住吉踊りが終わる頃は午後3時を廻っていたでしょうか。
住吉大社の田植え祭は、伊勢とは全く違った雰囲気の神事で非常に興味深かったです。
・神宮(伊勢の神宮、別宮である伊雑宮で行われる)
・香取神宮(千葉県)
・住吉大社(大阪府)
の3つ。学生のときに神宮のお田植祭は何度か拝見させてもらいました。今回は住吉大社の御田植神事に参列させていただきました。
まずは、第一本殿で祭典が執り行われます。また祭典に先立って奉仕する植女などに関する儀式もありますが秘事でもありここでは割愛。宮司の祝詞奏上が終わって、早苗が渡されるところから写真を交えて簡単に紹介します。

神前に供えた早苗が植女に渡されます。

次に神前に供えた水(神水)が大田主(耕作長)に渡されます。
この後、玉串拝礼があり、撤饌等の行事があり、第一本殿での神事が執り納めとなります。
この後、玉串拝礼があり、撤饌等の行事があり、第一本殿での神事が執り納めとなります。

宮司以下神職、そして御田植神事奉仕者、参列者が順に神田へと参進します。

御田に到着すると、まず田を大麻と塩湯で祓い清めます。

続いて、神水を田に注ぎ、神様のお力を田に戴きます。

植女が神前より頂いてきた早苗を替植女に渡します。

この間、斎牛によって田の代掻きが行われていました。

替植女に早苗が授けられると、いよいよ田植えが始まりました。

田植えが始まると、八乙女による田舞が奉納されました。

田舞の間も、早乙女や男衆によって田植えはどんどんと進みます。

御稔女(みとしね)による神田代舞が奉納されます。

鎧武者による風流武者行事が奉納されます。

雑兵に扮した子供たちによる棒打合戦が行われます。

童女による田植踊りが奉納されます。

住吉踊りが奉納されます。この頃にはすっかりと広い田に早苗が植えつけられました。
午後1時に第一本殿で祭典が執り行われ、住吉踊りが終わる頃は午後3時を廻っていたでしょうか。
住吉大社の田植え祭は、伊勢とは全く違った雰囲気の神事で非常に興味深かったです。
2011年06月17日
ブタのいた教室
今晩の金曜ロードショーで 「ブタのいた教室」 という映画が放送されます。
人が生きること、いのち、そういったことを考えさせられるので一度観たいと思っていた映画です。
子供たちが一体どういう結論を出すのか、結末にもとても興味があります。
是非、皆さんも観てみてください。
4月。6年2組の担任になった星先生(妻夫木聡)は、教室に仔ブタを連れてくる。「このブタをみんなで育てて、最後には食べようと思います」。先生の衝撃的な言葉で1年間の“命の授業"が始まった!しかし、26人の子供たちにとって仔ブタはかわいいペット。「Pちゃん」と名付けられクラスの一員になるが、タイムリミットは刻一刻と近付いていた。「Pちゃんを食べる?食べない?」究極の難問にクラスが出した答えとは…!?こういう内容の映画です。
http://tv.yahoo.co.jp/program/42760949/
人が生きること、いのち、そういったことを考えさせられるので一度観たいと思っていた映画です。
子供たちが一体どういう結論を出すのか、結末にもとても興味があります。
是非、皆さんも観てみてください。
2011年06月16日
2011年06月15日
お参りの作法
最近、20代30代の方々の神社参拝が増えているように感じています。
いろんなブームなどの影響もあるのでしょうが、単に浮ついた気持ちでお参りに来られる方ばかりでないので、きっかけは何であれ喜ばしいことだと思っています。
神社参拝の手順・マナーについても、いろいろなガイドブックやハウツー本に記されているので、手水を取ることや、神前では二礼二拍手一礼の作法で拝礼すること、また参道の中央はなるべく通らないようにすることなどは、結構皆さんご存知のようですし、きちっとされている方が多いです。
しかし、それ以外の部分についてはなかなか・・・。
例えばご祈祷の受付などを見ていて感じることがありますので、少し触れておきたいと思います。
まず、ご祈祷に際しての初穂料の納め方です。
本来初穂料というのは金額に決まりは無く、それぞれの心持で包んでくるものです。
しかし、代金という感覚の方が多いのか、割と お財布からそのまま現金が出てきて渡されることが多い のです。
神社での参拝に際する玉串料や祈祷料というのは神様へのお供えとするものですから、本来であればちゃんと袋に包み表書きをして持参をするものなのです。
結婚式のお祝いや、お葬式の霊前料・香典と同様に考えていただければわかりやすいのかもしれません。
お宮詣りでは、赤ちゃんに晴れ着を着せます。正確には赤ちゃんを抱いている人の肩から掛けてあげるのですが・・・。
この晴れ着を着せるタイミングが、お祓いの時や本殿に入ってからという場合が多く見受けられます。
正式には受付を済ませた時点で準備をします。手水を取る前に支度をしてしまうのが正しい作法だとは思いますが、当神社では控え室内で手水が取れますので、準備のしやすさなどから手水後に晴れ着を着せるところまでは良しとしています。
いずれにしても、神前に進むときからお参りははじまっているのです。
ご神前で晴れ着を着せるのは、いわば結婚式で新郎が高砂の席に着いてから羽織や上着を着るのと同じと思ってもらえばわかりやすいでしょうか?
最近、特に気になる参拝時の作法について2点ほど記してみました。
参考になればと思います。
いろんなブームなどの影響もあるのでしょうが、単に浮ついた気持ちでお参りに来られる方ばかりでないので、きっかけは何であれ喜ばしいことだと思っています。
神社参拝の手順・マナーについても、いろいろなガイドブックやハウツー本に記されているので、手水を取ることや、神前では二礼二拍手一礼の作法で拝礼すること、また参道の中央はなるべく通らないようにすることなどは、結構皆さんご存知のようですし、きちっとされている方が多いです。
しかし、それ以外の部分についてはなかなか・・・。
例えばご祈祷の受付などを見ていて感じることがありますので、少し触れておきたいと思います。
まず、ご祈祷に際しての初穂料の納め方です。
本来初穂料というのは金額に決まりは無く、それぞれの心持で包んでくるものです。
しかし、代金という感覚の方が多いのか、割と お財布からそのまま現金が出てきて渡されることが多い のです。
神社での参拝に際する玉串料や祈祷料というのは神様へのお供えとするものですから、本来であればちゃんと袋に包み表書きをして持参をするものなのです。
結婚式のお祝いや、お葬式の霊前料・香典と同様に考えていただければわかりやすいのかもしれません。
お宮詣りでは、赤ちゃんに晴れ着を着せます。正確には赤ちゃんを抱いている人の肩から掛けてあげるのですが・・・。
この晴れ着を着せるタイミングが、お祓いの時や本殿に入ってからという場合が多く見受けられます。
正式には受付を済ませた時点で準備をします。手水を取る前に支度をしてしまうのが正しい作法だとは思いますが、当神社では控え室内で手水が取れますので、準備のしやすさなどから手水後に晴れ着を着せるところまでは良しとしています。
いずれにしても、神前に進むときからお参りははじまっているのです。
ご神前で晴れ着を着せるのは、いわば結婚式で新郎が高砂の席に着いてから羽織や上着を着るのと同じと思ってもらえばわかりやすいでしょうか?
最近、特に気になる参拝時の作法について2点ほど記してみました。
参考になればと思います。
2011年06月14日
2011年06月13日
田植えの様子
昨日の田植えの様子が 「山東まちづくり会」のサイト に掲載されました。
泥んこ遊びや神事、そしてたけのこまんの田植えの様子が載っています。
是非、ご覧ください。メニュー左側の「まち会アルバム」から見られます。
【山東まちづくり会】http://sando.kinokuni-web.net/
泥んこ遊びや神事、そしてたけのこまんの田植えの様子が載っています。
是非、ご覧ください。メニュー左側の「まち会アルバム」から見られます。
【山東まちづくり会】http://sando.kinokuni-web.net/
2011年06月12日
田植え行事
朝から少し雨が降っていましたが、今日は山東まちづくり会の田植え行事です。
子供たちに泥遊びと田植えを体験してもらおうと企画しました。
折角なので、子供たちにお米作りの大切さなどを知ってほしいと、田植祭を行うことにもしました。地図はこちら
まずは田んぼをお祓いして、子供たちが泥んこ遊び。
今日ばかりはそういう主旨のイベントですから、どれだけ泥だらけになってもお母さんからおこられることはないと、子供たちは目一杯泥まみれになって遊んでいました。

1時間ほどの泥遊びの後、シャワーで泥を落としてお田植え祭。代表の子供たちに早苗が渡され、子供たちは並んで田植えをしました。初めての経験に最初はなかなか進みませんでしたが、慣れてくると比較的早いスピードで田植えが進められました。
山東地区のマスコットキャラクターである たけのこまん も田植えに参加してくれました。
たけのこまんは、田植えだけでなく、神事において重要な斎串を立てる行事も行いました。


最初、子供たちは田植え作業にすぐに飽きてしまうのではないかと心配していましたが、参加してくれた子供たちは最後まで植え付けをしてくれました。結構楽しかったみたいです。
最後に、参加してくれた子供たちには たけのこまんパン のプレゼントがありました。

今回田植えをした田んぼでは、秋に稲刈り行事も計画しています。
是非、ご参加下さい。多分、たけのこまんも稲刈りに駆けつけてくれます。
雨は、みんなが集まる時間には上がり、一通りの行事を終えて概ね片づけが終わった頃にまた振り出しました。
子供たちに泥遊びと田植えを体験してもらおうと企画しました。
折角なので、子供たちにお米作りの大切さなどを知ってほしいと、田植祭を行うことにもしました。地図はこちら
まずは田んぼをお祓いして、子供たちが泥んこ遊び。
今日ばかりはそういう主旨のイベントですから、どれだけ泥だらけになってもお母さんからおこられることはないと、子供たちは目一杯泥まみれになって遊んでいました。

1時間ほどの泥遊びの後、シャワーで泥を落としてお田植え祭。代表の子供たちに早苗が渡され、子供たちは並んで田植えをしました。初めての経験に最初はなかなか進みませんでしたが、慣れてくると比較的早いスピードで田植えが進められました。
山東地区のマスコットキャラクターである たけのこまん も田植えに参加してくれました。
たけのこまんは、田植えだけでなく、神事において重要な斎串を立てる行事も行いました。


最初、子供たちは田植え作業にすぐに飽きてしまうのではないかと心配していましたが、参加してくれた子供たちは最後まで植え付けをしてくれました。結構楽しかったみたいです。
最後に、参加してくれた子供たちには たけのこまんパン のプレゼントがありました。

今回田植えをした田んぼでは、秋に稲刈り行事も計画しています。
是非、ご参加下さい。多分、たけのこまんも稲刈りに駆けつけてくれます。
雨は、みんなが集まる時間には上がり、一通りの行事を終えて概ね片づけが終わった頃にまた振り出しました。
2011年06月11日
2011年06月10日
大人気、たけのこまん
伊太祁曽神社の鎮座する、和歌山市伊太祈曽という土地は山東(さんどう)という地域になります。
中世には山東荘と呼ばれ、根来寺の荘園であったとか。
この山東地区を活性化させようと 「山東まちづくり会(略して山東まち会)」 が結成され、日々活動しています。
私もその一員です。
この 山東まち会 のイメージキャラクターとして たけのこまん というのがいます。
このキャラクターがなんだか大ブレイクしているのです。
「ボクは変態じゃない!」あの【たけのこまん】のツイッターがすごいことに(和歌山県)
http://yurui.jp/
ちょっと方向性が微妙ですが、あの せんとくん だって最初は不評でしたから・・・。
あとは たけのこまん だけでなく、山東地域も注目されるようになればと思います。
中世には山東荘と呼ばれ、根来寺の荘園であったとか。
この山東地区を活性化させようと 「山東まちづくり会(略して山東まち会)」 が結成され、日々活動しています。
私もその一員です。
この 山東まち会 のイメージキャラクターとして たけのこまん というのがいます。
このキャラクターがなんだか大ブレイクしているのです。
「ボクは変態じゃない!」あの【たけのこまん】のツイッターがすごいことに(和歌山県)
http://yurui.jp/
ちょっと方向性が微妙ですが、あの せんとくん だって最初は不評でしたから・・・。
あとは たけのこまん だけでなく、山東地域も注目されるようになればと思います。
2011年06月09日
コレくらいは知っていてくれないと・・・
枝野長官、今上陛下が第何代か「知らない」 (産経新聞) - Yahoo!ニュース
枝野幸男官房長官は6日の参院決算委員会で、現在の天皇陛下が第何代なのかについて「知らない」と述べた。天皇陛下は初代神武天皇から数えて125代目にあたる。枝野氏は今年が皇紀何年(2671年)にあたるかも答えられなかった。山谷えり子氏(自民)に対する答弁。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110606-00000562-san-pol
天皇陛下は日本国の象徴としていらっしゃいます。
国政に携わる方が、それも行政府の長たる首相の補佐官がコレをご存知ないとは・・・。
枝野幸男官房長官は6日の参院決算委員会で、現在の天皇陛下が第何代なのかについて「知らない」と述べた。天皇陛下は初代神武天皇から数えて125代目にあたる。枝野氏は今年が皇紀何年(2671年)にあたるかも答えられなかった。山谷えり子氏(自民)に対する答弁。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110606-00000562-san-pol
天皇陛下は日本国の象徴としていらっしゃいます。
国政に携わる方が、それも行政府の長たる首相の補佐官がコレをご存知ないとは・・・。
2011年06月08日
駿河屋
和歌山市の老舗和菓子屋さんです。正式には「総本家駿河屋」だそうです。(以下「駿河屋」と表記します)
当神社の撤下神饌は駿河屋さんの和歌浦煎餅(玉子煎餅)です。焼印は当神社専用のものですが。
駿河屋さんは、もともと「鶴屋」といい、寛正年間に京都で創業したそうで、現在のような堅い練羊羹を開発した菓子屋とも伝えられているそうです。
天正年間に行われた豊臣秀吉による北野大茶会の引き出物として振舞われた「伏見羊羹」というのも、「鶴屋(後の駿河屋)」の羊羹だったとか。
その鶴屋は、やがて徳川家康とともに駿河国(静岡県)に移り、さらに徳川頼宣の紀州移転に従い紀州(和歌山県)に移ってきたそうです。そして紀州徳川御用達の菓子屋とされたといいます。
やがて、5代将軍徳川綱吉の長女鶴姫が紀州藩主嫡男の綱教にお輿入れの際、同じ名前は恐れ多いとして「鶴屋」の名称を「駿河屋」と変えたそうです。
当神社の撤下神饌は駿河屋さんの和歌浦煎餅(玉子煎餅)です。焼印は当神社専用のものですが。
駿河屋さんは、もともと「鶴屋」といい、寛正年間に京都で創業したそうで、現在のような堅い練羊羹を開発した菓子屋とも伝えられているそうです。
天正年間に行われた豊臣秀吉による北野大茶会の引き出物として振舞われた「伏見羊羹」というのも、「鶴屋(後の駿河屋)」の羊羹だったとか。
その鶴屋は、やがて徳川家康とともに駿河国(静岡県)に移り、さらに徳川頼宣の紀州移転に従い紀州(和歌山県)に移ってきたそうです。そして紀州徳川御用達の菓子屋とされたといいます。
やがて、5代将軍徳川綱吉の長女鶴姫が紀州藩主嫡男の綱教にお輿入れの際、同じ名前は恐れ多いとして「鶴屋」の名称を「駿河屋」と変えたそうです。
2011年06月02日
和歌山憲法研究会
「和歌山で憲法について勉強する会をつくろう」 という動きがあり、私にその発起人に名を連ねて欲しいというお話が来ました。
私は憲法は法律については何ら詳しくないのですが、いろいろなご縁で是非にというお話でしたので浅学菲才で微力ながらもお仲間に入れてもらうことにしました。
昨晩は発会準備のための第1回目の会合でした。
発起人の皆さんの目指す方向性の確認をし、「和歌山憲法研究会」が発足しました。
なんか、すごく大層な名前に少し緊張しますね。
憲法というのは国の基本です。これが元になって法律も作られて行くわけですからね。
パソコンでいうと、WindowsとかLinuxなどのOSみたいなものです。(う~ん変なたとえかな?)
”憲法研究会”という名前にはなっていますが、憲法だけの勉強をするのではなく、日本の国とは一体どういう国なのか。
これからどういう方向に向かって行かなくてはならないのか、などということも勉強してゆく会になりそうです。
自分たちの子供や孫、そして子孫のために、よい日本を残すための勉強をする会にしようということで、全員一致しました。
とても楽しいことになりそうです。
私は憲法は法律については何ら詳しくないのですが、いろいろなご縁で是非にというお話でしたので浅学菲才で微力ながらもお仲間に入れてもらうことにしました。
昨晩は発会準備のための第1回目の会合でした。
発起人の皆さんの目指す方向性の確認をし、「和歌山憲法研究会」が発足しました。
なんか、すごく大層な名前に少し緊張しますね。
憲法というのは国の基本です。これが元になって法律も作られて行くわけですからね。
パソコンでいうと、WindowsとかLinuxなどのOSみたいなものです。(う~ん変なたとえかな?)
”憲法研究会”という名前にはなっていますが、憲法だけの勉強をするのではなく、日本の国とは一体どういう国なのか。
これからどういう方向に向かって行かなくてはならないのか、などということも勉強してゆく会になりそうです。
自分たちの子供や孫、そして子孫のために、よい日本を残すための勉強をする会にしようということで、全員一致しました。
とても楽しいことになりそうです。
2011年06月02日
割烹ちひろ
昨晩、とある会合の会場で初めて寄せてもらいました。
以前から名前は知っていましたし、一回行ってみたいなぁと思いながら、なかなか機会がなかったのです。
とっても雰囲気のよいお店でしたし、料理もおいしかったです。