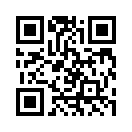2020年03月10日
御朱印帳の取り扱い
平成から令和に御代替わりの時、多くの神社では御朱印を求める参拝者で溢れかえっていました。
わずか1年足らず前の出来事です。
その少し前から御朱印ブームというのは始めっていたが、御代替わりを境に尚一層著しくなった気がします。
御朱印を神社仏閣から頂いてきてインターネットオークションなどで転売する輩が顕著になったのもこの頃でしょうか。
御朱印の受け方や御朱印帳の扱い方等については、様々なところでいろいろと記されているのでそちらに譲るとして、今回話題にしたいのは持ち主がいなくなった御朱印帳の扱いについてです。
まずは 『神社新報』 の以下の記事をご覧ください。
(画像の下に一部抜粋してテキスト化しています)

《 抜 粋 》
(前略)
御朱印は本来納経といって、社寺参拝の折に般若心経一巻を書写奉納した証のものであったのだから、せめて大祓詞一巻の書写奉納を義務付けるほどの信仰心が必要なのだらうが、その声は聞こえてこない。
だが流行はいつか廃れるし、熱心に社寺を巡拝して御朱印を集めた人も年をとる。さう考へるとこの流行が醒めた、今後ある時に大量に御朱印帳が処分される時期が来るといふことである。故人の意を汲んで社寺に納めてお焚上げにするならいいが、これが古紙として回収されることはいかがであらうか。御朱印は神札と同様のものとの考へもある。
流行が去り、所有者が亡くなったら、それは過去の旅の記憶に過ぎず、本人以外には無用のものとならう。そしていつか平成から令和に及ぶこの時期の御朱印が大量に古道具屋に出廻ったり、廃棄される時が来るのである。
(中略)御朱印帳は神仏の参拝の証であり、単なる名所巡りのスタンプ帳とは違って、粗末に扱ふものではないといふこと。また所有者の歿後も、その神聖性を保持し、処分にあたってはせめてお焚上げをするべきであるとの二点をぜひとも啓発せねばならない時期になってはゐまいかと思ふのである。
御朱印を集めて回る人たちの中には、一部不心得者がおり、その少数派の方々の行動が原因となって一部の神社では朱印を書くことを取りやめたり、朱印帳の扱いについて独自の規則を設けているところがあります。(中には神社の独自規則が行き過ぎているように見受けられる場合もあるが・・・)
そういった不逞の輩については今回は触れず、大多数のちゃんと神社仏閣を参拝して御朱印を集めて回っている方々の朱印帳についてのお話です。
御本人は信仰心を持ち、敬虔なものとして御朱印帳を扱っていたとしても、御本人が亡くなった後、果たしてその御朱印帳はどの様な扱いをされるのだろうかというのが、この投稿に記されたところです。
これまで、御神札やお守りについては、故人が祀っていた、所有していたものについて、その扱いが記されているものもありました。
改めて記すならば、
授かった神社や仏閣に出向いてこれまで護っていただいた御礼の参拝をして、その神社仏閣に御神札やお守りを返却する。
遠方などで上記が行えない場合は、やむを得ず近くの神社仏閣に持参してお焚上げを依頼する。(神社のものは神社へ、お寺のものはお寺へ)
また、故人が病に臥せっていた場合で、家族親族や友人が病気平癒の祈願などを行っていた場合は、当該神社仏閣に詣でて帰幽(亡くなったこと)奉告を行うこと。
ということです。
近年までこれほどまでの御朱印ブームはありませんでしたから、御朱印帳についてこの様な記述はなかったのだと思います。
また、仮にそこまで書かれていなくても、故人の思いを汲み取って、ご遺族は然るべき処置をするだろうという憶測もあったと思います。
もし、身の回りで御朱印帳の遺品が出てくることがありましたら、然るべくよろしくお願いいたします。
勿論、神社仏閣に持参してお焚上げをするだけが方法ではありません。
その朱印帳を引き継いて、各地の神社仏閣の御朱印を集める(特に全国一の宮朱印帳などの類)のも1つの方法ですし、故人の思いが詰まったものとして末永く保管しておくのも1つの方法です。
1つだけ願うとすれば、ゴミとして処分することだけは夢々なさりませんように・・・。