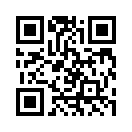2016年07月04日
国歌斉唱 その2
前回も国歌斉唱という題で記事を書きました。
今回 「その2」 としていますが、続編ではありません。
今夏、ブラジルのリオデジャネイロでオリンピックが開催されますね。
そして、その4年後が東京オリンピックです。
日本は次回オリンピック開催国ということで、良い成績を修めたいところです。
代表選手のモチベーションも高まっていることと思います。
そんな中、日本代表選手の壮行会が行われました。
その中で、東京五輪組織委員会会長で元首相の森喜朗氏が 「国歌を歌わない選手は日本の代表ではない」 という主旨の苦言を呈したとの記事がありました。
以下に、2つの記事をピックアップしておきます。
この2つの記事を見比べると、マスメディアの取材力にも問題が伺えます。
前者では「国歌斉唱」と記され、後者では「国歌独唱」と記されています。記事から推察すると「国歌独唱」だったようです。
国歌独唱として行われたのであれば、森氏の発言は見当違いの物言いになります。
しかし、君が代は 独唱 ではなく 斉唱 こそがふさわしいと 森氏は感じるからこその苦言であったと理解したいと思います。
この辺り、割りとこの方言葉足らずというか、説明不足というか、揚げ足の取られる物言いをされますね・・・。
国際試合などの開会セレモニーでは両国の国歌を演奏する場面をよく目にします。
この場合、多くが国歌独唱になっているように感じます。
私の個人的な印象ですが、国歌独唱になっているのは日本などで外国の国歌を演奏する場合だけでなく、その母国で行われる場合も同様なのが多いように感じます。
日本でも国歌君が代を独唱にするのは、そういった諸外国を真似しているからなんでしょうかね。
前回も記したように、現在の国歌君が代は、斉唱することを意識して作曲されているように私は感じています。
国歌君が代の成立過程については、このブログでも随分と以前に紹介しましたが、ここに改めて当該部分を抜粋しておきます。
冒頭のユニゾン、これこそが日本の国歌としてふさわしいと。
私は、国歌君が代に関しては、(少なくとも日本国内において演奏する際には)決して 「独唱」 などを行うのではなく、「斉唱」 にして欲しいと切に思うのです。
君が代作曲の経緯については過去記事 「 国歌『君が代』の成立過程 」 をご参照下さい。
今回 「その2」 としていますが、続編ではありません。
今夏、ブラジルのリオデジャネイロでオリンピックが開催されますね。
そして、その4年後が東京オリンピックです。
日本は次回オリンピック開催国ということで、良い成績を修めたいところです。
代表選手のモチベーションも高まっていることと思います。
そんな中、日本代表選手の壮行会が行われました。
その中で、東京五輪組織委員会会長で元首相の森喜朗氏が 「国歌を歌わない選手は日本の代表ではない」 という主旨の苦言を呈したとの記事がありました。
以下に、2つの記事をピックアップしておきます。
森喜朗氏、五輪壮行会で選手団に説教「国歌を歌わない選手は代表ではない」
8月のリオデジャネイロ五輪に出場する日本代表選手団の結団式と壮行会が3日、代々木競技場で行われた。体操、陸上など300人近い各団体の代表が出席した中、20年東京五輪組織委員会の森喜朗会長(78)が“説教”する場面もあった。
壮行会の冒頭の国歌斉唱で、代表選手の中で歌わなかった選手がいたことに「なぜ歌わないのか。サッカーのなでしこジャパンや、ラグビーのW杯は選手たちが君が代を思い切り歌った姿が感動を呼んだ。口をモグモグするのではなく、口を大きく開けて国歌を歌ってほしい。国歌を歌わない選手は日本代表ではない」と、苦言を呈した。
「国歌歌えない選手、日本代表じゃない」森喜朗氏
「国歌を歌えないような選手は日本の代表ではない」。東京・代々木の体育館で3日にあったリオデジャネイロ五輪の代表選手団の壮行会で、2020年東京五輪・パラリンピック組織委員会の森喜朗会長が来賓のあいさつでそう述べた。
壇上には選手ら約300人が登壇。森会長は、直前の陸上自衛隊中央音楽隊の松永美智子陸士長による国歌独唱時の様子を振り返って「どうしてみんなそろって国歌を歌わないのでしょうか」と問いかけ、サッカー女子の澤穂希さんや、ラグビーの五郎丸歩選手が君が代を歌い、その様子を見て国民が感動した、と述べた。「口をモゴモゴしているだけじゃなくて、声を大きく上げ、表彰台に立ったら、国歌を歌ってください」と選手団に呼びかけた。
場内ではみんなで声を合わせて歌う「斉唱」ではなく「国歌独唱」とアナウンスされ、ステージ上のモニターにも「国歌独唱」と表示されていた。
この2つの記事を見比べると、マスメディアの取材力にも問題が伺えます。
前者では「国歌斉唱」と記され、後者では「国歌独唱」と記されています。記事から推察すると「国歌独唱」だったようです。
国歌独唱として行われたのであれば、森氏の発言は見当違いの物言いになります。
しかし、君が代は 独唱 ではなく 斉唱 こそがふさわしいと 森氏は感じるからこその苦言であったと理解したいと思います。
この辺り、割りとこの方言葉足らずというか、説明不足というか、揚げ足の取られる物言いをされますね・・・。
国際試合などの開会セレモニーでは両国の国歌を演奏する場面をよく目にします。
この場合、多くが国歌独唱になっているように感じます。
私の個人的な印象ですが、国歌独唱になっているのは日本などで外国の国歌を演奏する場合だけでなく、その母国で行われる場合も同様なのが多いように感じます。
日本でも国歌君が代を独唱にするのは、そういった諸外国を真似しているからなんでしょうかね。
前回も記したように、現在の国歌君が代は、斉唱することを意識して作曲されているように私は感じています。
国歌君が代の成立過程については、このブログでも随分と以前に紹介しましたが、ここに改めて当該部分を抜粋しておきます。
エッケルトの編曲は、日本伝統の音楽に和音がなかったことを踏まへ、その特性を活かした素晴らしいものだった。最初と最後の二小節の伴奏は和音をつけずユニゾンで奏する。つまり「♪きみがよは」まではユニゾンで、「♪ちよに」からハーモニーが付けられ荘厳さを醸し出してゐるのだ。エッケルトは次のやうにも語ってゐる。「『きみがよは』の部分はたとひ千万人集まって歌はうとも、いかほど多数の異なった楽器で合奏するにしても、単一の音をもってしたい。ここに複雑な音を入れることは、声は和しても日本の国体に合はぬ気がする、云々」。
冒頭のユニゾン、これこそが日本の国歌としてふさわしいと。
私は、国歌君が代に関しては、(少なくとも日本国内において演奏する際には)決して 「独唱」 などを行うのではなく、「斉唱」 にして欲しいと切に思うのです。
君が代作曲の経緯については過去記事 「 国歌『君が代』の成立過程 」 をご参照下さい。
Posted by 木霊 at 09:31│Comments(0)
│ちょっとしたつぶやき
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。