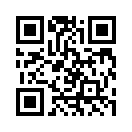2014年09月22日
日本語は融通無碍(ゆうづうむげ)
タイトルの「融通無碍(ゆうずうむげ)」が解らない・・・。
そういうお声もあるかもしれません。
ゆうずう-むげ【融通無碍】
[名・形動]考え方や行動にとらわれるところがなく、自由であること。また、そのさま。「―な(の)考え」「―に対処する」
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/224315/m0u/

さて、こんな画像をFacebookに友人がUPしていました。(右写真)
そういうお声もあるかもしれません。
ゆうずう-むげ【融通無碍】
[名・形動]考え方や行動にとらわれるところがなく、自由であること。また、そのさま。「―な(の)考え」「―に対処する」
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/224315/m0u/

さて、こんな画像をFacebookに友人がUPしていました。(右写真)
広島の土産物屋で薦められて購入したものだそうで、牡蠣のオイル漬けだそうです。
ラベルには 「花瑠&花星」 と記されて、その下に仮名で 「おいる&おいすたー」 と書かれています。
瑠は、瑠璃(るり)などと用いる文字ですので、もともと ”る” と読めます。
星はその意味から、英語のstar(スター)と掛けて読ませたのもわかります。
問題は ”花” という文字を ”おい” と読ませられるのかということなんですが・・・
花魁!そう 「おいらん」 からとったのであろうと辿り着きました。
もっとも 花魁 と書いて おいらん と読むのであって、花=おい、魁=らん ではないのですが・・・。
実はこの日、別の友人は 鰹料理の写真を載せて 「かつお」 なんだろうか 「かつを」 なんだろうか、と書いていました。
本来の日本語表記では 「かつを」 ということになりますが、現代仮名遣いでは 「かつお」 です。
なんで、こんなことになっているかと言いますと、戦後の占領政策に原因があります。
占領軍は日本語の解体も計画したようで、最終的には表音式仮名遣い(つまり ひらがな か カタカナ 場合によっては ローマ字)へ移行させることを考えていたようです。
その準備段階として、それまでの仮名遣いを廃止し、現代かなづかいを行うようにします。
昭和21年11月16日の内閣訓令第8号で、国語表記は現代語音にもとづいて整理するように定めます。
そのことにより教育の負担が軽くなり、国民の生活能率を上げ、文化水準を高めることができると説いています。
つまり、耳に聞こえる音の通りに文字を書き記すことにしたわけです。
それまでに使われていた仮名遣いは 「歴史的仮名遣い」 と呼ばれるようになって行きます。
具体的にいうと、
けふ → きょう 、 てふてふ → ちょうちょう
などといったぐあいです。この時に、「かつを」 も 「かつお」 と改まったという訳ですね。
ただ例外として、「私は」 とか 「この本を」 といった助詞だけは例外として、音通りに 「私わ」 とか 「この本お」 という表記にしなかったのです。
そうそう、冒頭に記した 融通無碍 も 本来仮名で書くと ゆうづうむげ となるはずなのですが、ゆうずうむげ で良いことになっています。
”じ” と ”ぢ” や ”ず” と ”づ” は音が同じですが、本来はきちっと使い分けていましたが、いまは 音を充てるので・・・。
”じ” と ”ぢ” や ”ず” と ”づ” は音が同じですが、本来はきちっと使い分けていましたが、いまは 音を充てるので・・・。
だから、鼻血 は はなじ でも はなぢ でも良いことになります。でも はなじ では 鼻血 に変換してくれませんでした。ゆうずうむげ は 融通無碍 に変換してくれるのに・・・(ちなみに ゆうづうむげ でも変換しました。)
現代かなづかい とあわせて 当用漢字表の実施 というのが行われます。
今は 当用漢字 という区別が無くなりましたが、私たちが子供のころはありました。
当用漢字 の意味は 当面用いてよい漢字 ということです。つまり最終的には漢字を排除しようという意図で生まれた訳です。
今は 当用漢字 という区別が無くなりましたが、私たちが子供のころはありました。
当用漢字 の意味は 当面用いてよい漢字 ということです。つまり最終的には漢字を排除しようという意図で生まれた訳です。
いうまでもなく占領軍は表意文字を持ちません。日本もアルファベットのような表音文字だけを用いる文化に改変しようとしたいたのでしょう。
ですから、日本が主権を回復した時に国語表記も元に戻せば良かったのでしょうが、いかんせん歴史的仮名遣いに比べると、現代かなづかいはわかり易く、また漢字も簡略されたため読みやすくなったとも言われます。
一節では、新聞など印刷物に使用するインクの量が大幅に節約できるようになるため、また漢字の画数が減るため文字が見やすくなるため、出版業界が現代かなづかいを大いに後押ししたとも言われます。
そして、ご丁寧にも昭和61年7月1日には 現代かなづかい を廃止して、新たに 現代仮名遣い を第2次中曽根内閣が定めます。
しかしその基本的な方針(現代語の音韻に従って書き表す事)は変わりありません。
靖國神社への首相参拝の件でもそうですが、どうしてこの人は余計なことをするのでしょう・・・。
ちなみに、当用漢字の方は、昭和56年にこれらを基にした 常用漢字 に改められました。
但し、当用漢字はもともと漢字使用の制限(つまり当用漢字以外の漢字は使用しないのが望ましい)として定められましたが、常用漢字は 法令、公文書、新聞、雑誌、放送等、一般の社会生活で用いる場合の漢字の目安 とされています。
という訳で、本来の日本語としては 歴史的仮名遣いということなりますが、戦後は教育されていないため正しく用いることができる人は少なくなっています。
かくいう私も正しく歴史的仮名遣いができるかというと、できません・・・。勉強します。
尚、新聞などは 現代仮名遣い と 常用漢字 で書き記すのが ”常識” なのでしょうが、歴史的仮名遣いで発刊されている ”非常識” な新聞が現在も存在しています。
神社界の業界新聞ともいえる 「神社新報」 がそれです。純然たる業界紙という訳でもありませんので、一般の方でも購読は可能です。毎週月曜日発刊の週刊新聞です。
神社界の業界新聞ともいえる 「神社新報」 がそれです。純然たる業界紙という訳でもありませんので、一般の方でも購読は可能です。毎週月曜日発刊の週刊新聞です。
興味のある方は、こちらの公式サイトをご覧ください。歴史的仮名遣いを用いる理由についてはこちら。
さて、冒頭から話が随分とズレてしまいましたが、日本語というのは表意文字(漢字)と表音文字(ひらがな・カタカナ)を用い、さらにはアルファベットやローマ字も取り混ぜて記載ができます。そして縦書きでも横書きでも書き記すことができます。
それ故に、星をスターと読ませることもできるのですね。さすがに花魁を分解して読ませたのには驚きましたが。